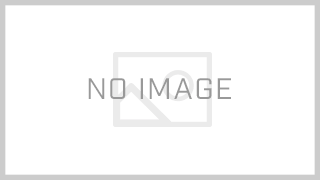今もまだ健在な父ではあるが、週に3回の人工透析を行い、歩き方にも力がなく、母親と
並んで歩いていると、知らない人からは、母の父親であるかのように誤解されることさえ
ある。
そんな父は、自分が小学校3年生の頃、「このままでは、あと半年も生きられないよ」と
医師に言われたことがあった。
あらゆる検査の数値が「生きている人間のそれではない」程悪かったようだ。
子供心に、それは大変ショックなことだった。
検査、や、医師、の、絶対的な価値なんてものは、まだ理解出来ない年齢ではあったが、
「人が死ぬ」ということについては、漠然とした恐怖を覚える年齢にもなっていて、父の
いなくなる世界だけが、毎日、布団に潜ってからも自分に襲いかかってきた。
「死」を自分にも置き換えるようになっていた。
孤独、暗闇、絶望… 棺の中にいる自分。そのままお墓の下に入れられ、土をかけられるが、
自分はまだ生きている。そこは真っ暗で、一生懸命声をあげても、誰にも聞いて貰えない。
起き上がろうとしても、窮屈で自由にならず、手で蓋を開けようとしても、びくともしない。
いつまでも続く孤独の中で、自分の絶叫だけが響いている。
ほんとに、ほんとに、それは恐ろしい世界で、いま、自分が孤独をとても嫌がり、寂しがり屋
な性格をしているのは、その当時の恐怖が、大きく影響しているのだろうと思う。と、同時に、
その死生観が、毎日、一日一日を生きているということの意味を考えるきっかけにもなって
いるのではないだろうか。
病気や高齢だからとて、死が近いわけでもない。健康な、若い人でさえ、あっけなく事故や
事件で逝ってしまうこともある。
人生なんて、生まれたときにはもう、カウントダウンが始まっているものなのだ。
いま、自分は毎日を後悔することなく、一生懸命生きていられるのかどうか。
そんな自問自答を繰り返すとき、この決意の「原点」になったトラウマを、ふと思い出した。
なんとなく、そんなことをblogに書いてみたくなった自分は、強い決意の中にいるのか、
弱りつつあるのか、さて、いったい、どんな表情をしているのか、まだよくわからずにいるが、
どうか、希望を見出そうとする情熱だけは、見失うことなく持ち続けていたいと思う。
雑感。 失礼いたしました。